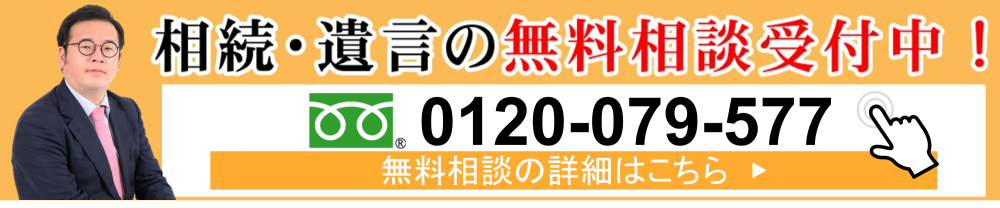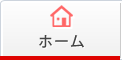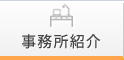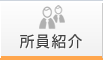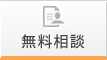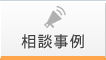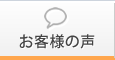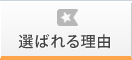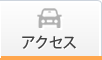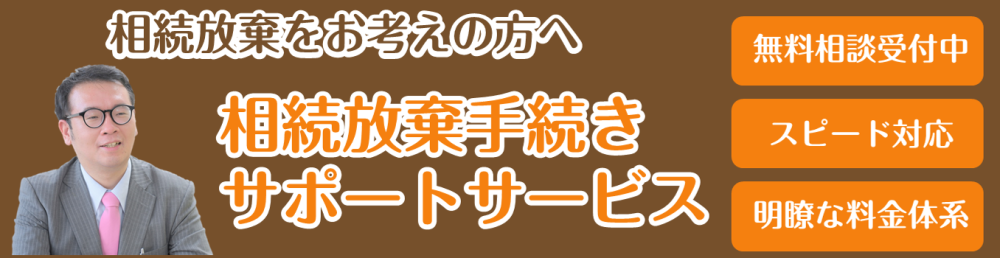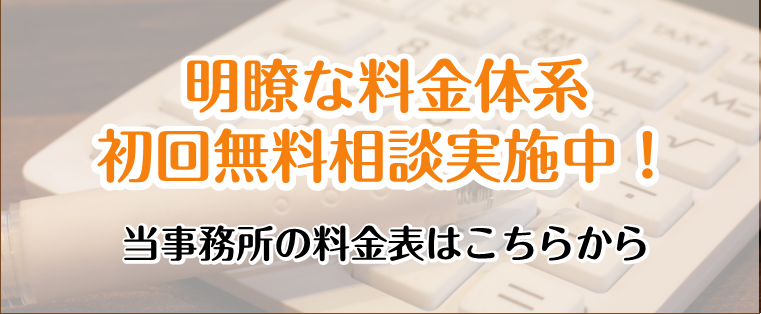こんな時どうする?相続放棄を行う人が認知症の場合
突然ですが、皆さんは自分の親の認知能力を把握してますでしょうか?
実は、認知症になってしまうと様々な手続きが無効なものになってしまうため、できなくなります。
「相続手続き」においてもその一つです。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要になりますが、相続人の中に認知症の方がいた場合は、後見人などを立てない限り手続きを進めることができません。
本記事では相続放棄と認知症について解説しますので是非ご参考にしてください。
当事務所では、無料の相続相談を実施しております。こんな場合どうしたらいいの?といった疑問点をお持ちの方はぜひこの機会にご利用ご検討ください。
相続の無料相談の流れと詳細はこちら≫
認知症の人がいる場合の相続放棄は

相続放棄をする人が認知症で判断能力がないような場合に相続放棄出来るのでしょうか。
認知症の人が相続人にいる場合の問題点についてみていきましょう。
(1)相続放棄ができない
結論から申し上げますと、相続放棄はできません。
認知症の人は判断能力が減退している状態ですので、相続放棄を選択すると返答していても、自分自身の判断ではないとみなされます。
特に昏睡状態では意思無能力等と考えられ、そもそも相続が開始したことを知らないという扱いを受けます。
相続放棄ができる期間は3カ月ですが、起算日である相続の開始を知った日が来ないため、そもそも期間が開始されません。
では、どうするかというと後見人を選任することで、相続放棄の期間が進み始めます。
しかし後見人でも相続放棄を希望しない可能性もあります。
(2)遺産分割協議への参加ができない
相続が発生し遺産分割協議を実施するときには、相続人全員から内容を理解した上での合意を得なければいけません。
その証拠として、最後に遺産分割協議書へ相続人全員が署名・押印するのが一般的です。
また自力での署名・押印が難しい相続人に関しては、内容をよく説明し確認した上で、署名の代筆もやむを得ないとされています。
ただし代筆が認められるのは、あくまでも相続人が理解している場合です。
認知症により遺産分割協議の内容を十分理解できていない状態では、遺産分割協議書へ署名・押印があったとしても、意思能力を欠くものと判断され、無効になる可能性があります。
相続放棄をするには成年後見制度を活用
認知症の相続人が相続放棄をするには『成年後見制度』を活用します。
成年後見制度とは、後見人となった人が、相続人の代理で相続放棄を申し立てる制度です。
ただし親族内で後見人を選ぶと、利益相反となる可能性に注意しなければいけません。
後見人には専門家(司法書士、弁護士等)がなれますし、親族もなることが出来ます。
後見人の申立ては家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
その後、相続放棄の手続きを行っていくという2段階のステップがあります。
成年後見人の熟慮期間について

相続放棄出来る期間は「被相続人(死亡した人)の死亡を知り、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」です。
しかし後見人が相続放棄する場合には、後見人が選任されて被相続人の死亡を知ってから3か月になります。
そのため、後見人の選任手続き中に3か月の期間が経過するという心配はありません。
後見人選出について基本的なケースを紹介!

後見人は親族以外が選ばれることが多い
後見人は家族の方がなりたいというケースが多いですが実際に成年後見人として選任される人は『約8割』が親族以外です。
また本人の現金・預貯金・株式など流動資産が『1,200万円以上』あるときには、財産の適切な管理のために専門家(司法書士など)が選ばれます。
親族が後見人になるケースが少ないのは『利益相反』になる可能性があるからです。
次項で詳しく説明します。
親族が後見人になる場合
親族が後見人になることは出来ますが、利害関係が対立する場合には利益相反となり、後見人として相続放棄出来ません。
例えば、父親(A)がいて死亡して、多額の借金があった場合に母親(B)が認知症で、その子供(C)がいる場合で考えてみましょう。
Aに多額の借金があったので、Bが相続放棄する場合には後見人の選任が必要です。
そこでCが後見人になった場合です。
Cも相続人なので相続放棄することができますが、CがBと同時又は先に相続放棄していない限り利益相反になり、Cが後見人として相続放棄することは出来ません。
C自身がBより先に相続放棄を済ませておくことが望ましいといえます。
民事信託(家族信託)による相続対策
家族信託とは、財産の利益を受ける権利と、財産を運用管理できる権利を分け、運用管理する権利のみを子供(家族)などの相続人に渡すことで、認知症になっても財産が凍結されることを防ぐことができる制度です。
家族信託の基本的な仕組みは、「委託者」「受託者」「受益者」で行われます。
委託者:財産のもともとの所有者で、財産を信託する人(本人)
受託者:財産の管理・運用・処分を任される人(家族など)
受益者:財産所有の権利を持ち、財産から利益を受ける人(一般的には本人)
メリット
財産の凍結を防ぐことができる
認知症になると、判断能力がないと判断されるため、様々な契約行為や意思決定ができなくなります。
家族信託を利用し、財産の利益を受ける権利と財産を運用する権利を分ければ、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができますので、財産の管理を任せた人(本人)が認知症になっでも、財産の凍結を防ぐことができます。
柔軟な財産管理をすることができる
法定後見制度と比較して、民事信託では柔軟な財産管理をおこなうことができます。
法定後見制度では、財産を処分・売却など行いたい場合は家庭裁判所の許可を得る必要があり、
許可がなければ、財産を処分することはでません。
一方で、民事信託(家族信託)では受託者(家族など)が財産の管理運用責任を持つため、契約上事前に決めた範囲内で、自由に財産を管理することができます。
認知症になる前に、民事信託契約を行えば自由な財産管理を行うことができますので、
事前に対策をすることが重要です。
相続人に認知症の人が含まれる場合の対策とは
(1)遺言書で認知症の人以外に相続させる
遺産分割協議は必ず実施しなければいけないものではありません。
被相続人が生前に遺言書を作成しており、誰に何を引き継がせるか明確であれば、そのまま相続することが可能です。
認知症の相続人がいると遺産分割協議の段階でつまずきがちです。
遺言書を作成しておく方法であれば、他の相続人へ負担をかけずに相続を進められます。
ただし遺言書は絶対ではありません。
相続人全員が遺言書の内容に反対する場合には、遺産分割協議で相続財産を分割する方法もあります。
ただしこの場合は、認知症の相続人も含め全員の同意が必要になってきます。
(2)遺言執行者を設定しておく
『遺言執行者』を選定し、遺言書の中に盛り込んでおくのも有効な手段です。
成年後見制度に精通した専門家へ依頼すれば、トラブルを未然に避け、スムーズに相続を進めることができます。
司法書士に遺言執行者を依頼するときの報酬は一律ではありません。各司法書士が自由に決められるため、あらかじめ遺言書で定めておきます。
また遺贈で不動産を受け取る人がいる場合も、遺言執行者を選定しておくのがおすすめです。相続人以外が引き継ぐ不動産であれば、遺言執行者が名義変更の登記申請を実施できます。
不動産の遺贈を受ける人が認知症であったとしても、確実に財産を移転できる方法になります。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
|
項目 |
意味 |
|---|---|
|
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
|
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
|
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
|
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
|
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
当事務所では、その他相続の相談も受付しております。相続には期限があるものもございますので、相続が発生した場合は
専門家への早めの相談をおすすめしております。
2024-10-14
- 相続放棄とは
- 相続放棄手続きサポート
- 【司法書士が解説!】相続放棄が出来ないケースとは?対処法と合わせて解説!
- 3か月過ぎた相続放棄
- 相続放棄と代襲相続
- 保険金の受け取りについて
- 債権者への対応
- 【司法書士が解決】相続放棄と入院費用の取扱いについて
- 家屋の取り扱い
- 年金の取扱い
- 日用品を処分する場合
- 司法書士が解説!相続放棄する場合、滞納家賃に支払い義務はある??
- こんな時どうする?相続放棄を行う人が認知症の場合
- 農地の取り扱い
- 退職金の取扱い
- 遺族年金、未支給年金の取扱い
- 遺産分割との関係
- 相続放棄と限定承認
- 預金の取扱い
- 相続放棄の取消し
- 相続放棄の必要書類
- 注意点について
- 相続放棄の範囲、順番
- 相続放棄の費用
- 限定承認について
- 相続放棄対策
- 【司法書士が解説!】相続放棄後の相続人の義務と相続財産管理人について
- 相続放棄手続きの管轄
- 相続放棄期限の延長
- 未成年者がいる場合
- 負債の調査
- 単純承認
- 相続放棄Q&A
- 相続放棄の判断
- 相続放棄をするなら
- 必要書類の取得方法